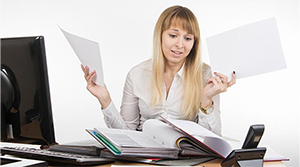25/02/13
学生納付特例「追納しなかった」場合、年金いくら減るのか あとから年金を増やす方法はある?

2024年末、「学生納付特例」を利用して年金保険料の支払いを先送りした学生のうち、わずか8.9%しか先送りした保険料をさかのぼって支払っていない実態が厚生労働省の審議会で明らかになりました。先送りした年金保険料を支払う人が少ない背景には家計の状況や年金制度への不信感などさまざまな事情があげられますが、先送りした年金保険料を支払える家計状況なのであれば、支払った方がいいでしょう。
学生納付特例の制度のあらましとメリット・デメリット、もしも先送りした年金保険料の支払いを行わなかった場合に、考えられる将来の影響について解説します。
そもそも国民年金保険料の学生納付特例制度とは?
国民年金保険料の学生納付特例制度(以下、学生納付特例)は、大学生や専門学校生など20歳以上の学生で、前年の所得が128万円以下である場合に利用できる制度です(社会保険料控除等があれば、基準となる前年所得金額は引き上がります)。
国民年金保険料の納付は原則として20歳から義務となりますが、届け出をすることによって在学中の保険料の支払いを先送りすることができます。先送りした期間は老後の基礎年金の受給資格期間に算入されますが、保険料の納付実績とは扱われないため将来受取る老後の基礎年金額は減額されます。ただ、後から先送りした年金保険料を納めれば先送りによる老後の基礎年金額の減額というペナルティは解消されるため、可能であればさかのぼって納付(追納)した方がいいでしょう。
ただし、注意したいのは、先送りした年金保険料をさかのぼって納められる時期には期限があるということです。原則として10年以内に納める必要があり、3年目以降は支払うべき年金保険料に加算額が加わります。
追納しなかった場合、年金はいくら減る?
追納しなかった場合、老後に受取る基礎年金額は減額されます。具体的にどれくらいの年金が減るのかを見てみましょう。
たとえば、4年間大学に通い、学生納付特例を2年間利用し、追納しなかった場合では、将来の老齢基礎年金額は満額である場合と比較して現在の価額で年間約4万円減るでしょう(老齢基礎年金の2025年度(令和7年度)の満額は83万1700円)。公的年金は原則として65歳から、生涯受取ることができるため、仮に30年間受給する場合では総額で120万円の差となることが予想されます。
一方、公的年金制度は財源に上限を設けつつ、現役世代が支払う年金保険料を給付にあてる「賦課方式」を採用していますから、もし先送りした年金保険料が納められなければ、年金財政の安定性がおびやかされる可能性があります。
年金保険料追納のメリット
一方、年金保険料の追納にはメリットもあります。最も大きなメリットは、確実に将来の年金額を増やせることでしょう。
例えば、先送りした2年分の年金保険料を追納すると、追納保険料総額約40万円に対し、将来の老齢基礎年金は現在の価額で年間約4万円増やすことができ、約10年で元をとれる計算となります。
加えて、追納の際支払った国民年金保険料は「社会保険料控除」の対象となるため、所得税・住民税の負担を軽くすることができます。仮に約40万円を追納した場合、所得税率10%の人なら所得税と住民税をあわせて約8万円の税金負担を減らすことができます。フリーランスや個人事業主の方は節税対策として活用できるでしょう。
追納しない場合でも年金は増やせる?
学生納付特例を利用した場合、追納することで将来の老齢基礎年金を増やすことができますが、実はそれ以外にも同様の効果を得られる方法はあります。以下の2つの方法です。
・60歳以降、厚生年金に加入して働く
・60歳以降、国民年金に任意加入する
60歳以降も厚生年金に加入して働くことができる方は、厚生年金保険料を納めることで基礎年金を満額まで増やすのと同様の効果を得ることができます。また、60歳以降厚生年金に加入しない方の場合も、「任意加入制度」を活用し、国民年金保険料を支払うことで満額まで年金額を増やすことができます。
ただ、いずれも将来に対策を先送りするもので、公的年金のしくみとして、将来支払う年金保険料は今よりも高いものとなる可能性はあります。ご自身のキャリアやライフプランと照らし合わせた上での検討が重要です。
年金保険料として支払うよりNISAで運用した方がいい?
年金保険料を後から払うというと、NISAを利用して自分で運用した方がいいのではないかと思われる方もいらっしゃることでしょう。確かに、仮に2年分の追納が必要であれば追納額は約40万円になりますから、年金保険料として支払わず自身で運用することも選択肢の1つです。
ただ、試算する際には、老後の公的年金は一生涯受け取れるという点をふまえておくことが重要です。
もし2年分を追納した場合、納付する保険料は約40万円で将来増やせる老齢基礎年金額は現在の価額で年間約4万円です。これを30年間受取ることができれば総額は120万円となり、3倍の成果を得られることとなります。
一方、同様の成果を自身が運用して得ようと思えば、年5%で複利運用できた場合でも23年、4%の場合であれば28年かかることが予想されます(40万円一括投資の場合)。
もちろんより長い期間運用したり、それ以上の良好な運用成績を上げ続けたりできれば、公的年金の受給額を上回る成果を得られる可能性はありますが、将来どうなるかは誰にもわかりません。
年金制度は5年ごとに財政検証を行い、長期的な年金財政の健全性を定期的に検証し、制度の持続性を維持する試みを行っています。2024年(令和6年)の財政検証の結果においては、もし今後継続的な経済成長が望める状況であれば、マクロ経済スライドによる調整が終了し、現在40歳以下の方が将来受取る老齢年金額の水準は今の高齢者より高くなる可能性も示されています。将来の年金額は物価上昇を100%カバーできるものではないものの、公的年金にはこのようなプラスの伸びしろの可能性も残されています。
将来の影響は不透明 キャリアや資産形成をふまえた選択を
よく年金は信用できないといった意見もありますが、現在年金制度はしくみを整え、持続可能な仕組みを維持できるよう定期的に行っている財政検証の結果をふまえ、議論が続けられています。
自身で運用しようとしても、もし途中で経済的に厳しい状況に陥ることがあれば、資金を引き出さざるをえず、年金を受取る時期まで運用を継続できない可能性もあるでしょう。一方年金保険料として納めれば、手取り所得を増やしつつ、否が応でも自身への還元は将来に先延ばしされるため、資金の確保は確実です。
年金「保険」料というように、本来公的年金制度は人生の大きな万が一への備える「保険」です。追納保険料を万が一にそなえる費用と考え、キャリア形成と資産形成といった視点をわすれずに自分にとっての価値を考えてみるといいのではないでしょうか。
【関連記事もチェック】
・年金生活者に1月届く「公的年金等の源泉徴収票」絶対確認すべき3つのポイント
・年金をもらいながら働いている人も「確定申告が必要」は本当か
・定年退職後でも失業給付はもらえるが、65歳「未満」と「以上」で金額は全然違う
・厚生年金「夫16万円・妻10万円」夫が亡くなると妻がもらえる年金はいくら?
・厚生年金で絶対やってはいけない5つのこと

内田英子 CFP,消費生活アドバイザー,住宅ローンアドバイザー
愛媛県在住。証券会社・保険ショップ勤務、専業主婦を経てひとり起業。現在、FPオフィスツクル(愛媛県松山市)代表。教育費から保険、住宅、資産形成、キャリア、相続まで幅広い視点で家計を診る家計の総合医として、ライフプランシミュレーションを駆使したファイナンシャルプランニングが強み。自治体や学校、団体・企業における金融教育講座も行う。

この記事が気に入ったら
いいね!しよう