25/07/06
年金収入のみの場合、所得税・住民税がかからないのはいくらまでか?
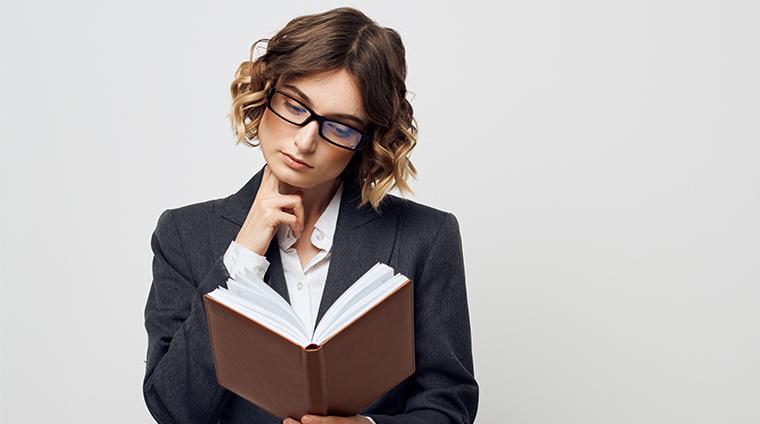
税金や社会保険に関する年収の壁。その壁を越えるかどうかで手取りに影響が出てきます。実は年金にも「年収の壁」が存在します。年金は老後の収入の柱なので、できれば税金を最小限にして手取りを増やしたいものです。
今回は、年金収入だけになった場合、年金収入がいくらまでなら税金がかからないのかを見ていきましょう。
所得税の計算のしくみ
収入が年金だけになったとしても、年金は雑所得なので一定金額を超えると所得税がかかります。公的年金を受け取る場合には、65歳未満の場合は60万円、65歳以上の場合には110万円の公的年金等控除を差し引いて雑所得の金額を計算します。公的年金のうち、障害年金、遺族年金は非課税で所得税がかからないので、所得計算には含みません。
年金の収入額から公的年金等控除額を差し引くと、公的年金等に係る雑所得金額が出てきます。ここから国民健康保険料や介護保険料などの社会保険料控除や扶養控除などの各種控除を差し引いたものが「課税所得金額」になります。この課税所得金額に5.105%(所得税5%×復興特別所得税1.021%)が課税されます。
<所得税の計算方法(年金収入の場合)>

筆者作成
所得控除とは
同じ収入があっても、その家庭によって生活環境が異なります。たとえば、扶養親族の数や病気・災害などによる出費など個人的な事情を考慮して所得金額から差し引かれる金額が所得控除です。
公的年金をもらう方なら所得控除のうち最低限、基礎控除が使えます。所得税の基礎控除は、令和7年分以後について改正されています。特に低所得者・中所得者は税負担を軽減させるために基礎控除額に上乗せがされています。また、令和7・8年分と令和9年分以後では、合計所得金額によって基礎控除額が異なる方もありますが、合計所得金額が132万円以下の場合には95万円が今後ずっと適用されます。
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直しについては、次のようになっています。
<基礎控除額(改正された範囲)>

国税庁資料より筆者作成
所得税はいくらまでならかかないのか
基礎控除の見直しによって、令和7年からは所得税において税金がかからない金額が変わります。公的年金等控除は年齢に応じて異なるので、所得税がかからない金額は65歳未満なら155万円、65歳以上なら205万円になります。
65歳未満 95万円+60万円(公的年金等控除)=155万円
65歳以上 95万円+110万円(公的年金等控除)=205万円
基礎控除と公的年金等控除を合わせた金額までの年金収入であれば、所得税はかかりません。
この基礎控除以外にも使える所得控除があれば、所得から差し引くことができます。その他の所得控除があれば、さらに所得税がかからない金額が引き上がることになります。年金収入から所得控除を差し引いてゼロになれば、所得税はかかりません。
令和7年度税制改正では、基礎控除の見直しの他に、給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の創設、扶養親族等の所得要件が改正されています。改正された部分は、面倒くさがらず確認しておくとよいでしょう。
<主な所得控除と控除額(令和7・8年分)>

筆者作成
住民税はいくらまでなら非課税か
年金収入だけでも一定額の所得金額以上になると住民税もかかってきます。住民税は、所得割と均等割で構成されていて、所得割と均等割の両方が非課税になる世帯のことを「住民税非課税世帯」といいます。住民税の所得割と均等割が非課税になるためには要件があり、以下のいずれかに該当しなければなりません。
(1) 生活保護法による生活扶助を受けている場合
(2) 障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の場合
(3) 前年の合計所得金額が以下の場合(1級地の例)
配偶者または扶養親族がいる場合 35万円×(扶養親族+1)+31万円
単身の場合 45万円
個人住民税の均等割における非課税限度額制度は、自治体によって基準額が異なります。それは、地域ごとの立地特性や生活様式などに応じて生じる物価・生活水準の差を基準額に反映させる「級地制度」を採用しているからです。おおまかには
1級地:東京都23区内、指定都市など
2級地:県庁所在地、一部の市町
3級地:一般市町村
という分類がされています。基準額は計算中における基本額や加算額について、2級地が1級地の0.9、3級地が1級地の0.8を乗じた金額をもとに条例で定めることになっています。
●非課税限度額の計算方法の例
・1級地
夫婦の場合 35万円×(扶養親族+1)+10万円+21万円=101万円
単身の場合 35万円+10万円=45万円
・2級地
夫婦の場合 31.5万円×(扶養親族+1)+10万円+18.9万円=91.9万円
単身の場合 31.5万円+10万円=41.5万円
・3級地
夫婦の場合 28万円×(扶養親族+1)+10万円+16.8万円=82.8万円
単身の場合 28万円+10万円=38万円
級地が異なると、住民税の非課税限度額の金額が変わります。級地が下になるほど住民税がかからない金額が引き下がります。同じ額の年金をもらっても、住んでいる自治体によって住民税がかかるかどうかが変わるのです。
この非課税限度額に公的年金等控除110万円(65歳以上の場合)を加えた金額は、下記の図表のようになります。この金額までの年金収入ならば、住民税はかかりません。3級地を例にとると、
・単身者の場合
所得が38万円以下
65歳以上の場合 年金収入で148万円
・夫婦世帯(配偶者控除あり)の場合
所得が82万8000円以下
65歳以上の場合 年金収入で192万8000円
ということになります。
<年金受給者の住民税非課税になる収入(65歳以上の場合)>

筆者作成
あくまでも計算例なので、詳しくはお住まいの自治体のウェブサイトなどで計算方法を確認するようにしてください。
なお、住民税が非課税になるかどうかは現在の収入状況ではなく、前年の合計所得金額で判定される点にご注意ください。特に、退職の翌年の収入は少ないのに住民税は高くなる場合が多いので、収入減を見越して前もって納税資金を確保しておくことが重要になります。
税金がかからないとどんなメリットがあるのか
年収が一定額を超えると所得税や住民税がかかり始め、手取りが減少します。年金収入では、住民税の賦課が国民年金保険料や医療費の自己負担額、介護保険料や介護サービス費の自己負担額にまで影響を与えます。
たとえば、住民税非課税世帯に該当すると、
・高額療養費の負担限度額が下がる
・高額介護サービス費の負担限度額が下がる
・介護施設を利用する場合の食費や居住費が下がる
・給付金をもらえることが多くなる
などのメリットがあります。
年を重ねると、病院や介護サービスのお世話になることが多いため、できるだけ支出が抑えられると、家計にゆとりが持てます。年金の受け取り方も選択肢が増えてきました。年金受取り時には、どんな税金のしくみになっているかを知り備えておくことで、老後の生活設計が立てやすくなります。ぜひ、税金の改正点はアップデートしておくことをおすすめします。
【関連記事もチェック】
・定年後「年金以外」にもらえるお金16選
・ねんきん定期便(年金定期便)に記載の年金額が突然数十万円増えた理由
・厚生年金が一番多くもらえる「最高等級」の人は意外と多い
・ねんきん定期便(年金定期便)「放置」絶対ダメ!届いたらすべきたった1つの行動
・年金に6万円上乗せされる「年金生活者支援給付金」対象者は?どうすればもらえる?

池田 幸代 株式会社ブリエ 代表取締役 本気の家計プロ®
証券会社に勤務後、結婚。長年の土地問題を解決したいという思いから、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)を取得。不動産賃貸業経営。「お客様の夢と希望とともに」をキャッチフレーズに2016年に会社設立。福岡を中心に活動中。FP Cafe登録パートナー

この記事が気に入ったら
いいね!しよう





























