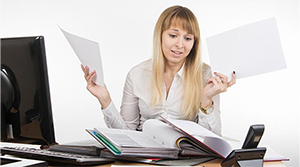25/03/31
【悲報】60歳以後賃金が大幅に下がるのに、高年齢雇用継続給付の支給率15%→10%へ【2025年4月から】

60歳以降も同じ会社で続けて働く人のうち、給与が大きく減る人に支給される高年齢雇用継続給付。4月から、高年齢雇用継続給付の支給率が下がり、減額されます。これにより、60歳を迎え、引き続き働こうと思っている方は、影響を受ける可能性があります。
給料にくわえ、高年齢雇用継続給付も下がるとなるとがっかりしますが、これまで多くのライフプランに関する相談を受けてきたFPとしては、重要なことは一時的な手当の減額に注目することではなく、その先のキャリアプランとライフプランであると考えます。
高年齢雇用継続給付の支給率15→10%へ
高年齢雇用継続給付は、60歳以降も継続して勤務し、給与が大きく減る場合に受け取れる手当です。高年齢雇用継続給付は、原則として雇用保険の加入期間が5年以上ある、60歳から65歳になるまでの一般被保険者を対象に、賃金額が60歳到達時の75%未満になった場合に支払われます。最高で賃金額の15%(賃金額が60歳到達時の61%以下になった場合)に相当する額を受け取ることができます。
2025年4月以降、高年齢雇用継続給付額の算出にあたって利用される支給率が引き下げられます。2025年4月からは、最高で賃金額の10%(賃金額が60歳到達時の64%以下になった場合)となります。この給付率引き下げにより、減額する支給額のシミュレーション結果は以下のとおりです。
【高年齢雇用継続給付のシミュレーション例①】
・60歳到達時等の賃金月額 494,700円
・60歳以降の賃金 300,000円
・賃金低下率 61%
◯支給額
2025年3月まで:45,000円 → 2025年4月以降:30,000円(15,000円減額)
【高年齢雇用継続給付のシミュレーション例②】
・60歳到達時等の賃金月額 400,000円
・60歳以降の賃金 290,000円
・賃金低下率 72.5%
◯支給額
2025年3月まで:6,525円 → 2025年4月以降:5,829円(696円減額)
高年齢雇用継続給付の減額の背景には、もはや70歳程度まで働くことが既定路線となりつつあるという社会的なキャリア観の変化があります。高年齢雇用継続給付は創設当初、定年年齢と年金受給年齢とのギャップをうめるために、65歳までの雇用継続を援助、促進することを目的として創設されましたが、近年多くの企業で65歳まで継続して働ける環境が整いつつあります。シニアの雇用安定に軸足を変え、給付を縮小しつつ、企業の賃金制度の見直しやシニア層への賃上げなど処遇改善を促す方向に舵を切ったのです。
なお、厚生労働省「令和7年1月雇用保険事業月報」によれば、高年齢雇用継続給付の受給者数は約25万9,000人で、就業者数の約0.4%、平均受給額は約52,000円(千円以下切り捨て)です。
高年齢雇用継続給付の金額の計算方法
高年齢雇用継続給付の金額はどの程度賃金が下がったかによって異なります。原則として「60歳以降の賃金月額×支給率」で求められます。
高年齢雇用継続給付の支給率は、賃金の低下率によって変わります。支給率の早見表は以下のとおりです。
<2025年3月31日まで>

厚生労働省資料より
<2025年4月1日から>

厚生労働省資料より
高年齢雇用継続給付が支払われない人は?
高年齢雇用継続給付には以下のとおり支給限度額が設けられており、対象月の賃金が支給限度額を超えていたり、下限を大きく下回っていたりする場合は、対象外となります。また、計算式に算入できる60歳到達時の賃金額にも上限があります。
●2025年度の支給限度額・賃金月額
・支給限度額 (最高)376,750円 (最低)2,295円
・60歳到達時等の賃金月額 (上限)494,700円 (下限)86,070円
2025年4月以降、高年齢雇用継続給付の手当額が減る人
高年齢雇用継続給付の支給率引き下げの影響を受け手当が減る可能性があるのは、2025年4月以降に支給を受ける方です。
高年齢雇用継続給付の減額幅は賃金低下率や賃金状況によって異なりますが、賃金が上限の範囲内なのであれば賃金低下率が高い方ほど大きくなります。特に大企業勤務の大卒男性は支給率減額の影響を大きく受ける可能性があります。平均賃金低下率が比較的大きいためです。
賃金構造基本統計調査を参照すると、以下のとおり60歳を節目とする賃金カーブはゆるやかになりつつあり、定年前後の給料の平均低下率は高年齢雇用継続給付の支給対象となる75%を下回っていますが、詳細に見ると属性によって差があります。
【60歳を節目とする給与の平均減額割合】
平成12年 男性26.7%、女性12.8%
令和5年 男性21.8%、女性12.5%
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より
高年齢雇用継続給付の給付率引き下げの理由
高年齢雇用継続給付の支給率引き下げの背景には、近年多くの企業で65歳まで継続して働ける環境が整いつつあり、制度創設当初の目的が達成されたことがあります。働く高齢者の数は右肩上がりに増加しています。
高年齢雇用継続給付は創設当初、定年年齢と年金受給年齢とのギャップをうめるために、65歳までの雇用継続を援助、促進することを目的として創設されました。しかし、法改正をへて、65歳まで雇用継続可能な環境が整ってきています。もはや70歳程度まで働くことが既定路線となりつつあるなかで、シニアの雇用安定に軸足を変え、給付を縮小しつつ、企業の賃金制度の見直しやシニア層への賃上げなど処遇改善を促す方向に舵を切ったのです。
なお、高年齢雇用継続給付の支給率の引き下げは2020年から決められていました。制度創設当初より支給率は段階的に引き下げられており、2003年の引き下げを経て、今回は2回目となりました。
求められるファイナンシャルプランの見直し
高年齢雇用継続給付の支給率引き下げの影響は、人によっては大きなものとなり、大きくなくともがっかりすることと思います。しかし、重要なことはその先の人生設計であり、高年齢雇用継続給付の減額をはじめとする様々なリスクを織り込んだうえで、ライフプランに活かしていくことです。
ライフプランに活かすためには、以下のようなアクションが必要となります
・老後生活のライフプランニング
・活用できる資産の棚卸し(金融資産・退職金・年金等)
・キャリアプランの見直し
・適切なファイナンシャルプランの策定
場合によっては、支給額減額よりももっと注目すべき課題が見つかることもあります。
特に、ファイナンシャルプランの策定にあたっては、「高年齢雇用継続給付の支給率引き下げとなった背景には、長く働くことが前提の社会になりつつある」という変化があることを、しっかりととらえておくことが重要です。
一般的なケースでとらえるのではなく、まずは試算をし、ご自身への影響を確認しましょう。そのうえで、今後の働き方やライフプランをふまえファイナンシャルプランを見直しましょう。ご自身だけでは難しいと思ったら、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することも検討してください。
【関連記事もチェック】
・定額減税の確定申告に要注意!記入忘れ→税金が増える可能性あり
・【知らないと大損】年金受給者が確定申告で得する8つのケース
・【知らないと大損】年金生活者の医療費控除「10万円以下」でも還付される
・【知らないと大損】年金生活者の医療費控除「10万円」超えてなくても還付される
・「ねんきん定期便見たら数十万円増額してた」年金額が増えた驚きの理由

内田英子 CFP,消費生活アドバイザー,住宅ローンアドバイザー
愛媛県在住。証券会社・保険ショップ勤務、専業主婦を経てひとり起業。現在、FPオフィスツクル(愛媛県松山市)代表。教育費から保険、住宅、資産形成、キャリア、相続まで幅広い視点で家計を診る家計の総合医として、ライフプランシミュレーションを駆使したファイナンシャルプランニングが強み。自治体や学校、団体・企業における金融教育講座も行う。

この記事が気に入ったら
いいね!しよう