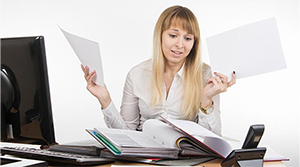25/04/16
iDeCo掛金「増額」で受取りタイミングで税金が増えるのはどんな人?

2025年度(令和7年度)の税制改正大綱には、iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)の変更点が盛り込まれています。これにより、iDeCo利用の柔軟性が高まる一方、出口での税制優遇の一部縮小が含まれていたことから、「iDeCoが改悪される」と話題になっています。ではiDeCoの出口、つまり受け取るときに税金が増えるのはどんな人なのでしょうか。iDeCoの変更点とともに紹介します。
入り口は緩和、出口は厳格化…iDeCoの変更内容
今回取り上げるiDeCoの変更により影響を受ける方は、以下のような方です。
・すでにiDeCoをしている方
・これからiDeCoを考えている方
・iDeCoや企業型確定拠出年金の他、退職金がある方
iDeCoの具体的な変更内容は以下のとおりです。
(1) iDeCoの拠出限度額が引き上げられる
iDeCoの毎月の掛金額には上限があり、働き方や企業年金の有無などにより異なります。今後、具体的には以下のように、拠出可能額が月7,000円~39,000円引き上げとなる予定でます。
【iDeCoの掛金】
・自営業者等第1号被保険者 月68,000円→月75,000円
・企業年金に加入する会社員 月20,000円→月62,000円から企業年金の掛金額を差し引いた金額
・企業年金がない会社員 月23,000円→月62,000円
拠出限度額の増額により積み立てられる金額が増え、柔軟な資産形成プランが可能になります。
(2) 60歳以降もiDeCoを続けやすくなる
これまでのiDeCoでは、加入が公的年金の被保険者の方に限られていたため、60歳以降iDeCoは使いにくいものでした。しかし、今後は以下のような要件をすべて満たすことで60歳以上も継続して積立ができるため、iDeCoを使いやすくなる見込みです。
【60歳以降もiDeCoを継続できる人】
・60歳以上70歳未満であって現行のiDeCoに加入できない人
・iDeCoに資産がある人(私的年金の資産をiDeCoに移換できる人を含む)
・老齢基礎年金およびiDeCoの老齢給付金を受給していない人
(3) いわゆる「5年ルール」→「10年ルール」に
退職金とiDeCoがある方がiDeCoを一時金で先に受け取る場合、10年以上間を空けなければ、退職所得控除を満額利用することはできなくなります。
これまでは、例えばiDeCoもしていて退職金がある、という方の場合、iDeCoを一時金で受け取った後、5年以上の期間を空ければ、退職金受け取り時に退職所得控除を満額使うことができました。いわゆる「5年ルール」です。しかし、「5年ルール」は「10年ルール」に変更される見込みです。出口での税制優遇の縮小と言えます。
5年ルール→10年ルールで影響を受ける人はどんな人?
5年ルールが10年ルールとなることは、大きな節税効果のある退職所得控除の利用要件の厳格化ともいえます。影響を受けるのは、以下の2つを満たす方です。
(1)退職金があり、iDeCoを利用している人
例えば、退職時には勤務先から退職金が支給され、あわせてiDeCoもある、といった退職金の準備が盤石で高額な方ほど影響を受けるでしょう。退職所得控除額は節税効果が高い一方、金額には限りがあるためです。
なお、iDeCoではなく企業型確定拠出年金を利用している方も同様です。企業型確定拠出年金はiDeCoと同じ法にもとづいて運用されているためです。
(2)iDeCoを受け取ってから退職金を受け取ろうと考えている人
10年ルールが適用されるのは、iDeCoや企業型確定拠出年金(以下、確定拠出年金)を退職金よりも先に受け取る人です。5年ルールが10年ルールとなることにより、税金が増える可能性があります。
もし5年ルールが10年ルールとなれば、手取り額が大きく減少する可能性があります。
「10年ルール」の影響を受けない人は?
10年ルールは、例えば、確定拠出年金(iDeCoや企業型確定拠出年金)のほかに退職金がない、といった方は今回の変更に影響を受けません。また、確定拠出年金を退職金よりも後に受け取ったり同じ年に受け取ったりする方も影響を受けません。
実際には確定拠出年金を退職金よりも先に受け取る場合も、今回の変更に影響を受ける方は少ないでしょう。会社員の場合、退職金の受取時期を自分でコントロールすることはできないため、節税のために5年以上空けて退職金を受け取る、ということをできる方が少ないためです。
該当するとすれば、大企業勤務の方や小規模企業共済とiDeCoを利用している個人事業主の方などでしょう。
10年ルール化への具体的な対策はある?
5年ルールが10年ルールとなることで影響を受ける方は、以下のような対策を検討しましょう。
●①退職所得控除額を確認する
確定拠出年金の一時金受取額と退職金額が退職所得控除額に収まるか確認しましょう。両方あわせた金額が退職所得控除額の範囲に収まるのであれば、iDeCoの受け取りを退職金と同じ年にすることで、退職所得控除を有効に使うことができます。
退職所得控除額は、
・勤続年数(加入年数)20年以下…40万円×勤続年数(加入年数)
・勤続年数(加入年数)20年超…800万円+70万円×勤続年数(加入年数)
と、会社の勤続年数または確定拠出年金の加入年数が多いほど多くなり、20年以下の部分では年40万円、20年超の部分では年70万円ずつ増加します。また、勤続年数(加入年数)1年未満の端数も繰り上げるので、たとえば勤続年数が30年と1日でも「31年」となります。
ただし、勤続年数と加入年数は合算できません。
統計によれば、iDeCoの1人あたり平均資産額は以下のとおり、多くとも500万円前後であり、平均的な退職金額は約1,600万円です。
【1人あたり資産額平均】
・iDeCo 70代471万円、60代337万円、50代188万円、40代121万円
・企業型確定拠出年金 60代534万円、50代477万円、40代268万円
(厚生労働省「確定拠出年金統計資料」(2024年3月末)より)
【退職年金制度併用企業の定年退職者の退職一時金平均額】
・約1,616万円(万円未満四捨五入)
(厚生労働省「令和5年賃金事情等総合調査」より)
iDeCoの老齢一時金の方が退職金よりもすくないなら、退職金よりも先にiDeCoを受け取る、というプランは考え直した方がいいでしょう。退職所得控除の利用を優先すべきは金額の大きい方です。
両方あわせた金額が退職所得控除額の範囲に収まらない場合は、iDeCoを一部年金受け取りとすることも検討しましょう。年金受け取りとすれば「雑所得」として公的年金と同じ扱いとなり、例えば65歳未満で年60万円など、一定の非課税枠が使える可能性があります。
●②掛金拠出期間を延ばす
iDeCoの資産がそれほど大きくない場合は、60歳以降もiDeCoに掛金を拠出しやすくなる今回の変更を活かし、掛金拠出期間を引きのばすことを検討してみましょう。iDeCoへの拠出限度額が引き上げられることで、iDeCoの拠出額に注目されがちですが、将来の税金負担を減らすために注目すべきは拠出額ではなく、拠出期間です。
筆者がこれまでライフプランに関するご相談を受けてきた中では、確定拠出年金で継続して投資を続けると、少額の積み立てであっても老後のライフプランの見通しが明るくなるといった効果を実感しています。
iDeCoには、リバランスを行いやすく、投資を長期でより継続しやすいといった強みがあります。また、拠出期間を延ばすことで、退職所得控除額を1年あたり40万円または70万円増やすことができます。
同様に、20代30代の方にとっても、拠出期間を延ばすという対策は有効でしょう。最近は転職が前提のキャリアプランを構築されている方は多く、退職金のある企業は少なくなってきています。iDeCoは転職しても継続でき、掛金拠出を続けやすいため、早く始めていればキャリアに関わらず、退職所得控除を着実に増やせることが期待されます。
求められるファイナンシャルプランの見直し
今回の変更により、iDeCoの入り口の緩和と出口の制限が進むことが見込まれます。引き続きiDeCoの掛金は全額所得控除となる点は変わりませんし、iDeCoに節税メリットがあることは確かです。
しかし、退職所得控除の額には限りがありますし、今回のような退職所得控除に関する制度改正は今後も考えられるため、特に制度改正といったリスクをふまえた上でのプランニングが求められます。「公平・中立な税」の名目のもと、老後生活資金という常識の範囲を大きく超えた受取額については、出口で相応の税負担を求める流れですので、iDeCoをつかった資産形成を考えている方はあらためて、iDeCoの使い方を見直すべきタイミングにあります。
前提として、節税効果を活かすためには、土台となるファイナンシャルプランが重要です。ファイナンシャルプランの策定にあたっては、ライフプランとキャリアプランがカギとなります。今後の動きに注目しながら、ライフプランとキャリアプランとともにiDeCoの使い方を含む、ファイナンシャルプランを見直すきっかけとしましょう。「ひとりでは手に負えない」と感じる場合は、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することも検討してください。
【関連記事もチェック】
・【四季報2025年2集春号】2025年度に飛躍期待の好業績株5銘柄【Money&YouTV】
・老後貧乏に陥る50代「激ヤバ行動」8選
・年金生活者の「手取り」は減り続けているという衝撃の実態【Money&YouTV】
・新NISAの積立日は何日がベスト?損する日はいつ?過去データで徹底検証してみた【Money&YouTV】
・絶対に手を出してはいけない「金融機関が儲かるだけ」の金融商品10選

内田英子 CFP,消費生活アドバイザー,住宅ローンアドバイザー
愛媛県在住。証券会社・保険ショップ勤務、専業主婦を経てひとり起業。現在、FPオフィスツクル(愛媛県松山市)代表。教育費から保険、住宅、資産形成、キャリア、相続まで幅広い視点で家計を診る家計の総合医として、ライフプランシミュレーションを駆使したファイナンシャルプランニングが強み。自治体や学校、団体・企業における金融教育講座も行う。

この記事が気に入ったら
いいね!しよう