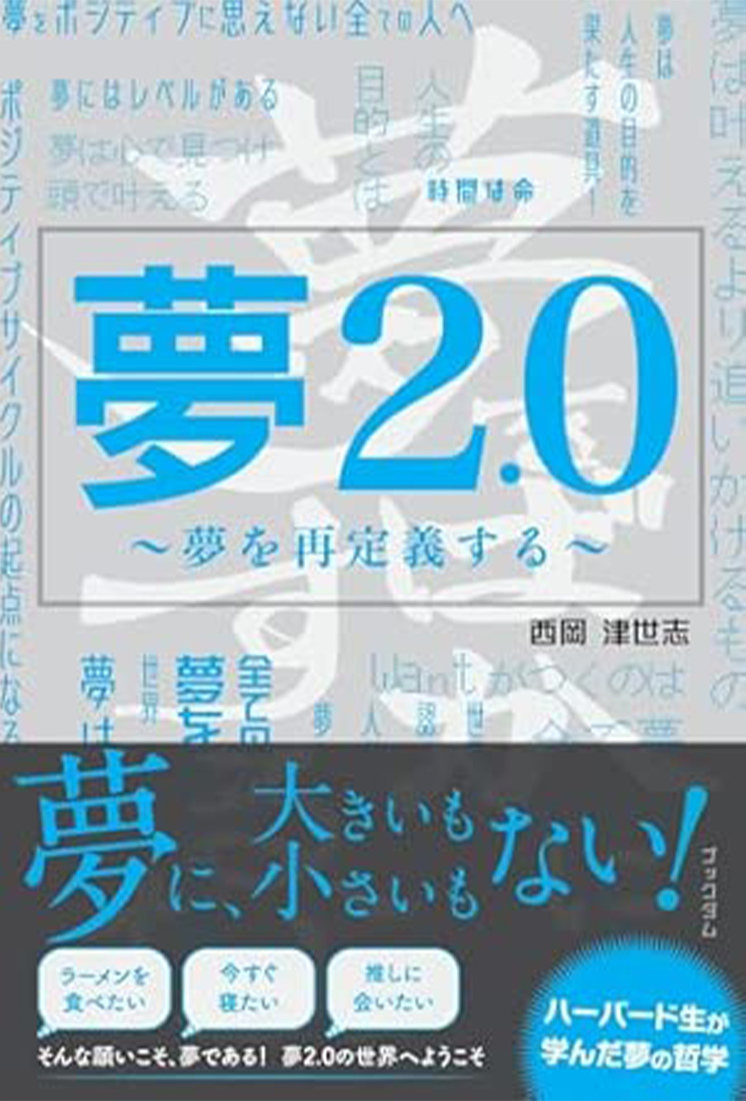25/10/07
夢の捉え方を変えれば人生が変わる『夢2.0~夢を再定義する~』
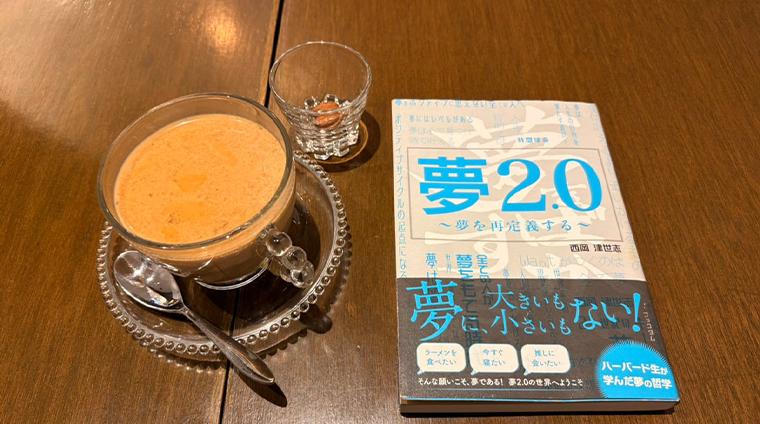
みなさんには夢がありますか?
「夢」と聞くと、多くの人は「将来就きたい理想の職業」を思い浮かべます。
しかしその結果、年齢や才能の壁を感じて「自分には夢がない」と諦めてしまう人も少なくないのではないでしょうか。
書籍『夢2.0~夢を再定義する~』(ブックダム)は、この「夢」の捉え方を変えることで、誰もが夢を持ち、希望を持って生きられる社会を目指します。
なぜ日本人は夢を持てないのか
企業が経営理念を掲げ、ミッションやビジョンを語る時代になりました。ビジネスの世界では、理想を掲げて行動することが当たり前になってきています。しかし個人レベルになると、日本人は夢を語ることに抵抗を感じる傾向があります。
本書の著者であり、お客が自分の夢を語ることができるラーメンチェーン「夢を語れ」CEOの西岡津世志氏は、夢に関する講演依頼を受けることも多いといいます。そういった講演で「夢はありますか?」と問いかけても、「ある」と答えるのは参加者の1割程度に過ぎないそうです。
著者はこの経験から、日本人が夢を持てない原因を探り、夢を「将来就きたい理想の職業」に限定してしまっていることだと分析しました。多くの人がサッカー選手、宇宙飛行士、社長——こうした大きな目標を夢と捉えがちだと考えたのです。
そうであるとするならば、年齢や才能の壁に阻まれ、多くの人は「自分は夢が持てない」と諦めてしまうでしょう。
「○○したい」を夢と定義する
本書が提唱する「夢2.0」は、この認識を根本から変えようとします。夢1.0が「将来就きたい理想の職業」で、才能ある一部の人だけが持てるものだとすれば、夢2.0は「心がワクワクするものすべて」であり、誰もが持てるものとします。
サッカー選手や宇宙飛行士ももちろん夢ですが、「今日、ラーメンが食べたい」「カレーが食べたい」といった「○○したい」=WANTも夢だと捉えることができます。そして著者は、夢は心から湧いてくるものだと説きます。この素直な「したい」という気持ちこそが、すべての夢の出発点なのです。
この定義なら、誰もが今すぐ夢を持ち、行動すれば叶えることができるでしょう。
夢のレベルは上がっていく
小さな夢を叶えることは重要で、夢は小さなものからだんだんとレベルが上がっていくと著者は説きます。
著者自身「ラーメンが食べたい」という小さな夢から始まり、「自分で作りたい」「店を開きたい」「独立したい」と夢のレベルが上がり、ボストンで「夢を語れるラーメン店」を実現。今では「全世界に夢を語れる場所を作る」という使命を追いかけています。
重要なのは、小さな夢をないがしろにして、いきなり高いレベルを目指しても到達できないということです。著者の経験で言えば、「ラーメンが食べたい」がなければ、「ラーメン店を開きたい」「海外に出店したい」という夢は生まれなかったはずです。小さな夢を一つずつ叶えることで、次の夢が自然に湧いてくる——夢はそういう仕組みになっていると説きます。
また、夢を叶える過程そのものを楽しむことの重要性も説かれています。最短距離で目標を達成することより、「どうやったら楽しく叶えられるか」を考えること。夢は叶えた瞬間だけでなく、追いかけている過程でも心をワクワクさせてくれるものだからです。
目の前の「○○したい」から始めよう
日々の忙しさの中で、私たちは「何がしたいか」を考える余裕を失いがちです。しかし本書は、そんな時こそ「今日は何が食べたい?」「週末はどこに行きたい?」という心の声に耳を傾けることの大切さを示しています。
「○○したい」という声を聞き、一つずつ叶えていく。そのシンプルな積み重ねが、やがて想像もしなかった場所へ連れていってくれるはずです。
希望を持って生きたいと願う人、何かに挑戦したいと思っている人、一度は夢を諦めたけれど再挑戦したい人に、本書は夢に関する新しい視点を与えてくれるでしょう。
【関連記事もチェック】
・定年後「お金と時間があっても」しなくていい5つのこと
・定年後貧乏を招く、退職金の使い方ワースト5
・お金が貯まらない家のキッチンに潜む「貧乏を招く」3つのモノ
・50代で買うと老後破産を招く6つのモノ
・貧乏人は頻繁に行くけど、お金持ちはほとんど行かない場所5選

三田智朗 株式会社ブックダム編集長
横浜市立大学卒業後、出版社にて書店営業を担当。3つの出版社で営業職を歴任し、20都府県・1000店舗以上での営業経験を持つ。12年間の営業キャリアを経て、2020年に自由国民社編集部へ異動。年間10~20点の書籍編集に携わり、累計4万部のベストセラーなど多数の書籍を手がける。2023年に編集長に就任し、2024年4月より株式会社ブックダムに編集長として参画。「読者の未来をめくる」をテーマに、営業と書籍編集で培った経験を活かし、コンセプトの設計と著者の強みを引き出すコンテンツづくりに取り組んでいる。
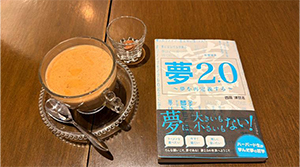
この記事が気に入ったら
いいね!しよう